こんにちは^^ひろです。
なぜブラームス
ブラームスとは何か
そう本日5月7日はみなさんご存じヨハネス・ブラームスの誕生日
ヨハネス・ブラームス(独: Johannes Brahms、1833年5月7日 – 1897年4月3日)は、ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。J.S.バッハ(Bach)、ベートーヴェン(Beethoven)と共にドイツ音楽における三大Bとも称される。ハンブルクに生まれ、ウィーンに没する。作風は概してロマン派音楽に属するが、古典主義的な形式美を尊重する傾向も強い[1]。
ベートーヴェンの後継者ととらえる人もおり、指揮者のハンス・フォン・ビューローは彼の『交響曲第1番 ハ短調』を「ベートーヴェンの交響曲第10番」と評した[2]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昨今の音楽シーンは縦横無尽に検索できて即再生が可能になりました。
ゆえに新しい音楽の中に古い音楽が再評価されることも多々あります。
最近でいえば日本のシティポップが話題になりましたよね。
そんな中古い音楽が評価されるならばいっそのこともう1世紀さかのぼってクラシックいこうやってことです。
ぐははははははh

林道と情熱の舞曲──ジムニーで聴くブラームス

先に述べた通り5月7日は、ドイツの作曲家ヨハネス・ブラームスの誕生日。
クラシック音楽の中でも重厚かつ情熱的な旋律を奏でた彼の作品は、現代においても多くの人に愛されています。
そんなブラームスの楽曲、実は私にとっても思い出深い存在です。
特に「ハンガリー舞曲 第5番」は、小学生の頃、音楽会で演奏したことがあり、当時の緊張と高揚感が今でも記憶に残っています。
ソロ部分(?)というか見せ場のミファソミ レミファレ ドレミド シドレシ と今思えば鉄板のシーケンス
(フラット2つなのでシ・ミはフラット)
私はイングヴェイ大好きなのでこの時から培われていた可能性も否定できません。
アコーディオンで弾いてましたが今思い返してもかっこよかったですね。
私も昔ギターで弾いてみたりしました。
ギターで弾くとミファソミとソからミが意外と難しいんですよね(雑魚ですみません)
ソからファに戻りたい衝動しか生まれません。
あとここまで言ってなんですがハンガリー舞曲は第1番が一番好きです。
ジムニーとクラシック、交わる瞬間

舗装されていない林道、左右から覆いかぶさる木々、タイヤが小石をはじく音。
その上を軽快に走るジムニーシエラの揺れと、ハンガリー舞曲の跳ねるようなリズム。
クラシック音楽というと「静かな部屋で座って聴くもの」と思われがちですが、実は“自然の中で聴く”ことで、その力強さや空間の広がりがより際立つのではないかと思いました。
ジムニーで走る林道は、予定通りにいかないからこそ面白い。
少しハンドルを切りすぎた、ギアをもう1段落としておけばよかった、そんな“ズレ”すらも愛おしく感じます。
クラシック音楽もまた、即興や揺れを含む“生きた音”だからこそ、そこに重なり合う感覚があるのかもしれません。
ブラームスの音楽が持つ“山道感”

ブラームスの作品は、どれも構築的でありながら、熱を内に秘めたような情熱を感じさせます。
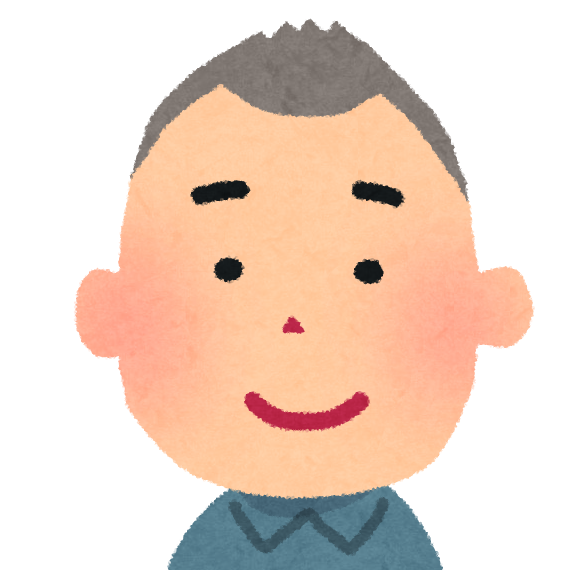
もちろん全部知っているわけではありません(キリッ
たとえば交響曲第1番などは、まるで険しい峠道を越えていくような展開で、途中に現れる希望のメロディが、頂上からの景色のように思える瞬間があります。
クラシックに詳しくなくても、ジムニーで走る“冒険”と音楽の“構築美”が、自然とリンクしていくのを感じるはずです。
なんとなく聞いたことある、くらいの知名度はあるはずなのでそういう些細なところを入口にするのもいいと思いますよ^^
おわりに──ジムニーのBGMにクラシックを

それでは今回ブラームス×ジムニーシエラをお送りしました。
今、私はジムニーのBGMとして、クラシック音楽を取り入れることに・・・特にハマってはいません()
どんな音楽を流そうともドライブと共に流れる旋律は、自然や路面と対話するような感覚を与えてくれます。
5月7日、ブラームスの誕生日をきっかけに、ジムニーとクラシックという異色の組み合わせが、新しい“走る時間”をくれました。
「ハンガリー舞曲 第5番」、ぜひ林道で一度聴いてみてください。車の振動とリズムがぴたりと合う瞬間、あなたの中でも何かが変わるかもしれません。
クラシック音楽は最初の一歩が中々踏み込みにくいものがありますが結構面白いと思うんですよね。
好きなアーティストのそのまた好きなアーティストとかをたどっていくと最終クラシックにたどり着くことありますのでそういったところからでも新しく古い音楽を発見できると思います。
ではでは皆様もよきジムニーライフを!ノシ


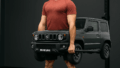
コメント